- トップ
- > 保護責任者遺棄(致死)罪について弁護士が解説
保護責任者遺棄(致死)罪について弁護士が解説
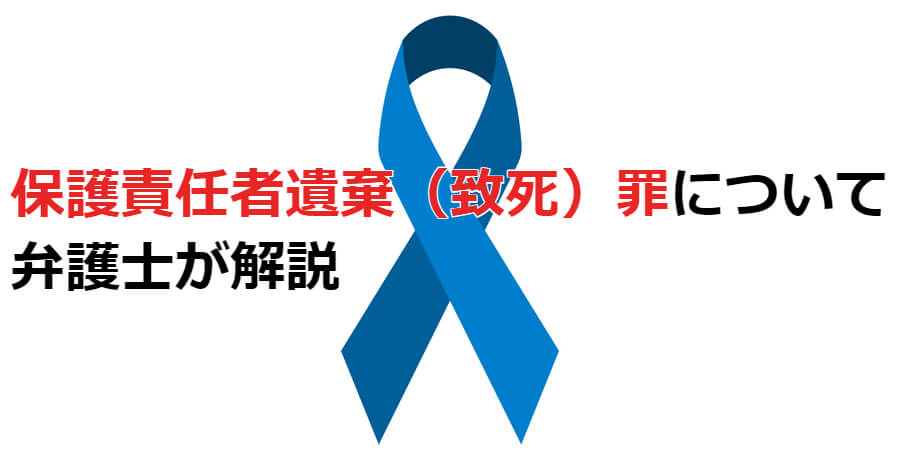
このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。
保護責任者遺棄とは
保護責任者遺棄とは、老年者、幼年者、身体障害者または病者を保護する責任のある者が、これらの者を遺棄したり、生存に必要な保護をしないことです。
保護責任者遺棄の被害者
1.「老年者」と「幼年者」
老年者や幼年者に該当するか否かは、年齢によって一律に決められるわけではなく、「扶助を必要とするか否か」という観点から実質的に判断されます。
介護なしに生活できない高齢者は扶助を必要とする者にあたります。幼児については、7,8歳未満であれば扶助を必要とすると判断される可能性が高いです。
2.「病者」
「病」は肉体的な病気だけではなく、ケガや精神疾患も含みます。判例では泥酔者も病者とされています。覚せい剤などの薬物を使用して錯乱状態にある人も病者になります。
全ての病者が保護責任者遺棄の被害者になるわけではありません。被害者になるのは、現に扶助を必要とする状態にある病者に限られます。
保護責任者遺棄の「保護責任」とは
保護責任者遺棄罪は一定の者を保護する責任がある者について成立する犯罪です。保護責任は、法令、契約、慣習、事務管理、条理によって発生するとされています。
1.法令に基づく保護責任
法令上の保護義務として以下のようなものがあります。
・親権者の子に対する監護義務(民法820条)
・親族の扶養義務(民法877条~)
・車の運転者の教護義務(道路交通法72条1項)
これらの法令に該当しても直ちに保護責任者遺棄罪の保護責任を負うわけではありません。刑法上の保護責任の有無は、被害者との関係や被害者が保護を必要とするに至った経緯等から個別に判断されます。
例えば、ひき逃げをしても直ちに刑法上の保護責任を負うわけではありませんが、被害者を助けるために自分の車に乗せた後に気が変わって車道に放置した場合のように、引き受け行為があれば保護責任が認められます。
2.契約に基づく保護責任
業務の性質から当然に保護義務が認められる場合は、契約書に保護義務が明記されている必要はありません。
例えば、病院での看護や高齢者の介護、ベビーシッターについては、対象者の生命や身体の安全を保護する義務が当然に含まれると考えられます。
3.事務管理に基づく保護責任
事務管理とは、義務がないのに他人のために事務の管理をすることです。簡単にいうと、おせっかいで人助けをすることです。
義務がないのに病人を自宅に引きとったケースで、事務管理により保護責任を認めた判例があります(大審院判例大正15年9月28日)。
義務がないとはいえ、いったんおせっかいを焼いた以上は最後まで責任をもって保護しなさいということです。
4.条理に基づく保護責任
法令や契約、慣習、事務管理によって保護責任を認めることはできないが、常識的に考えて保護責任を認めるべきケースです。判例では、条理によって以下の被害者に対する保護責任を認めています。
・加害者の運転する自動車から飛び降りて重傷を負った女性
・医師の堕胎手術によって出生した未熟児
・同棲していた女性の連れ子
・加害者が覚せい剤を注射したことにより錯乱状態になった少女
保護責任者遺棄の「遺棄」とは
保護責任者遺棄罪の「遺棄」には次の2つのタイプがあります。
①被害者の身体を物理的に移動させること(移置)
②被害者を置き去りにすること
単純遺棄罪の遺棄は①に限られますが、保護責任者遺棄罪の遺棄は、①だけではなく②も含みます。
【置き去りの具体例】
・病気で寝たきりの親を残して失踪した
・母が3歳の実子を放置して自宅を出て行った
・真夏に両親が車の中に子供を残したまま長時間パチンコをしていた
保護責任者遺棄の「生存に必要な保護」とは
被害者を遺棄すること以外に、生存に必要な保護をしなかったときにも保護責任者遺棄罪が成立します。
遺棄は、加害者が被害者を別の場所に移したり置き去りにすることによって物理的に距離をとることですが、加害者が被害者と同じ場所にいても、生存に必要な保護をしないときは、保護責任者遺棄罪が成立します。
不保護の典型的なケースは家庭内で親が幼い子供に食事を与えないことです。
保護責任者遺棄の罰則
保護責任者遺棄罪の罰則は、懲役3か月~5年です。
保護責任者遺棄の加重犯
保護責任者遺棄罪を犯して被害者にケガをさせた場合は、保護責任者遺棄致傷罪になります。保護責任者遺棄致傷罪の罰則は、懲役3月~15年です。
保護責任者遺棄罪を犯して被害者を死亡させた場合は保護責任者遺棄致死罪になります。保護責任者遺棄致死罪の罰則は。懲役3年~20年です。
保護責任者遺棄の時効は
保護責任者遺棄の時効は5年です。
保護責任者遺棄致傷の時効は10年です。
保護責任者遺棄致死の時効は20年です。
保護責任者遺棄致死と殺人罪の違い
保護責任を負う者が、殺意をもって、要保護者を遺棄したり、生存に必要な保護を与えなかった場合は、殺人罪が成立し、保護責任者遺棄致死罪は殺人罪に吸収されます。
殺意は、「殺す。」という確定的な故意だけではなく、「このままでは死ぬかもしれないがそれでもよい。」という未必の故意も含まれます。
医師の治療を受けさせなければ要保護者が死亡する可能性が高い状況で、そのような状況であることを認識しつつ、あえて放置した場合は、未必の故意が認められ、殺人罪が成立する可能性が高いです。
子供に食事を与えないで虐待を続け衰弱死させたケースで、殺人罪を認めた判例があります(さいたま地裁平成15年3月12日)。
保護責任者遺棄の刑事弁護
保護責任者遺棄は家庭内で生じることが多く、子どもが死亡したことがきっかけで刑事事件となり、逮捕・起訴されるケースが多いです。
日常的に児童虐待するなかで生存に必要な保護をせず死なせてしまった場合は、10年前後の実刑判決になることが多いです。
一方、若年の女性が自力で出産した後パニックになり、産まれたばかりの嬰児に必要な保護をせず死なせてしまったケースでは、執行猶予がつくことも少なくありません。
☑ 夫からDVを受け恐怖で仕方なく加担してしまった
☑ 日常的な虐待行為はなくふだんは育児をしていた
☑ 出産直後でパニックになり判断能力が鈍っていた
このような事情がある場合は弁護士が検察官や裁判官に主張します。




