- トップ
- > 執行猶予とは?執行猶予をとるための2つのステップを弁護士が解説
執行猶予とは?執行猶予をとるための2つのステップを弁護士が解説
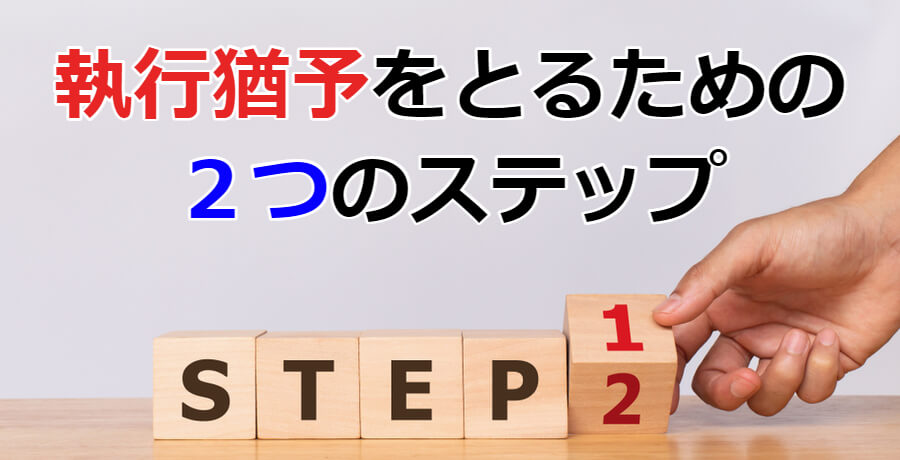
このページはウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。
執行猶予とは
1.執行猶予になれば家に帰れる
執行猶予とは懲役刑や禁固刑の裁判が確定しても、それらの刑罰がすぐに執行されないことです。そのため、執行猶予がつくと直ちに刑務所に入ることはありません。
2.執行猶予が取り消されることも
執行猶予になっても刑務所行きにならないことが確定したわけではありません。執行猶予の期間中に新たに刑事事件を起こして起訴され、その犯罪について禁固・懲役の実刑判決が確定すると、執行猶予が取り消されます。
3.執行猶予が取り消されると刑務所に
執行猶予が取り消されると、当初の懲役(禁固)と新たな犯罪の懲役(禁固)を合計した期間、刑務所に入らなければなりません。
4.無事に猶予期間が過ぎると自由の身に
執行猶予が取り消されることなく猶予期間が経過すると、刑の言渡しの効果が消滅します。そのため、執行猶予になった事件については刑務所に入らないことが確定します。
5.猶予期間は最長5年
執行猶予の期間は最短1年、最長5年です。「懲役2年・執行猶予4年」といったように、懲役刑(禁固刑)の期間よりも執行猶予の期間は長くなります。
執行猶予をとるためのステップ1
執行猶予をとるためには、前提として、次の(1)から(3)のいずれかに該当する必要があります。
(1)実刑判決を受けたことがない
(2)実刑判決を受けたことがあっても、刑の執行が終わった日(満期日)から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがないこと
(3)執行猶予期間中に判決が宣告される場合は、次の3つの要件を全て満たしている
① 当初の執行猶予について保護観察がつけられていない
② 今度の判決が1年以内の懲役刑または禁錮刑である
③ 特に酌量すべき情状がある
(1)から(3)のどれにも該当しない場合は、どんなに頑張っても執行猶予をとることができません。
(3)のケースで再び執行猶予になることを「再度の執行猶予」といいます。「ダブル執行猶予」と言われることもあります。
再度の執行猶予が認められると必ず保護観察がつけられます。再度の執行猶予を獲得するのは非常に難しいため、刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼した方がよいでしょう。
執行猶予をとるためのステップ2
1.裁判官が刑罰を決めるプロセス
ステップ1は執行猶予の前提条件です。そのため、ステップ1をクリアしたからといってそれだけで執行猶予をとれるわけではありません。
ステップ1をクリアした事件について、裁判官は次のプロセスで執行猶予にするか実刑にするかを決めています。
【プロセス①】 犯罪の手口や被害状況といった「事件そのものに関する事情」を考慮して刑罰の大まかな範囲を決定。 ↓ 【プロセス②】 示談などの「一般情状」を考慮して、プロセス①で決めた大まかな範囲のなかで、具体的な刑罰を調整 |
2.執行猶予のポイントは懲役3年
3年以下の懲役刑または禁錮刑でなければ執行猶予をつけることはできません。これは法律で決められたルールで例外はありません。
そのため、執行猶予をとるためには、裁判官が決めた「刑罰の大まかな範囲」の中に懲役(禁固)3年が含まれている必要があります。
「刑罰の大まかな範囲」の下限が懲役(禁固)3年を超えていると、どんなに一般情状が良くても執行猶予をとることはできません。
大まかな刑罰の範囲(第1プロセス) | 執行猶予の可能性 |
懲役2年~懲役4年 | 場合によっては執行猶予をとることが可能 |
懲役5年~懲役7年 | どんなに頑張っても執行猶予はとれない |
3.弁護士が主張・立証すること
弁護士は、「事件そのものに関する事情」と「一般情状」について、以下のような事情を主張・立証します。
【事件そのものに関する事情】
・行為が悪質ではない
・結果が重大ではない
・計画性がない
・被害者にも落ち度がある
【一般情状】
・被告人が反省している
・被害者との間で示談が成立している
・被害弁償を行なっている
・再発防止策をとっている
・家族のサポート体制がある
「事件そのものに関する事情」のなかでは、行為の悪質性と結果の重大性が特に重要です。「一般情状」のなかでは、示談が特に重要です。
執行猶予の相談は刑事事件に強い弁護士へ
実刑判決になれば刑務所に収容されます。そうなれば仕事を失い、残された家族も大きな影響を受けます。場合によっては妻や夫から離婚を切り出されるかもしれません。
執行猶予をとれるか否かで皆さまの人生が大きく変わってきます。ウェルネスの弁護士は、数多くの刑事事件を扱っており、ダブル執行猶予を獲得した実績もあります。
執行猶予はぜひウェルネス(03-5577-3613)の弁護士にご相談ください。
【関連ページ】




