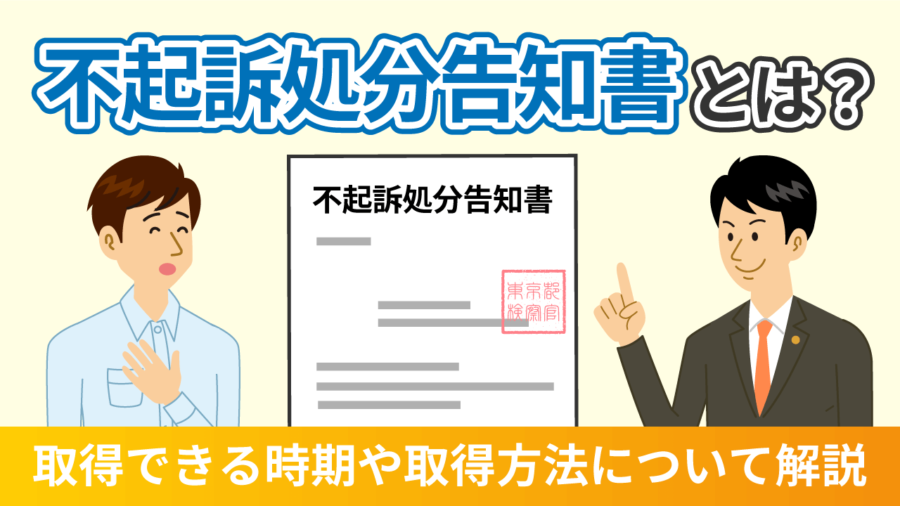- トップ
- > 不起訴処分とは?無罪との違いは?弁護士がわかりやすく解説
- > 不起訴処分告知書とは?取得できる時期や取得方法について解説
不起訴処分告知書とは?取得できる時期や取得方法について解説
不起訴になった場合は不起訴処分告知書という証明書を取得することができます。
このページでは不起訴処分告知書の取得のしかたや取得できるタイミング、取得費用などについて、弁護士 楠 洋一郎が解説しました。ぜひ参考にしてみてください!
不起訴処分告知書とは?
1.不起訴処分告知書の内容
不起訴処分告知書とは、捜査していた刑事事件を不起訴処分にしたことが記載されている証明書です。A4サイズの紙1枚に次の情報が書かれています。
①被疑者の氏名
②担当検察官の氏名
③犯罪名
④不起訴になったこと
⑤不起訴処分の日付
刑事訴訟法259条にもとづき被疑者からの請求があったときに発行される書面です。
【刑事訴訟法259条】 検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。 |
捜査の対象になっている方は、「自分はどういう処分になるのだろう?」と不安な気持でいっぱいのはずです。検察官から不起訴になったことを書面で証明してもらえれば、安心することができます。
2.そもそも不起訴とは?
不起訴処分告知書は不起訴になった事実を証明する書面ですが、そもそも不起訴とは何でしょうか?
不起訴とは犯罪の被疑者を刑事裁判にかけないことです。刑事裁判にかけられなければ有罪判決を受けることはありません。そのため前科もつきません。
刑事事件は警察の捜査を経て検察官に引き継がれます。検察官は事件について起訴するか不起訴にするかを必ず決めなければなりません。代表的な不起訴は次の3つです。
不起訴の種類 | 内容 |
起訴猶予 | 犯罪を立証できる証拠がある ⇒起訴できるが示談の成立等の事情をふまえ、あえて起訴しない |
嫌疑なし | 犯罪の嫌疑がない(真犯人がいる等) ⇒起訴するわけにはいかない |
嫌疑不十分 | 犯罪の嫌疑はあるが、犯罪を立証するだけの証拠がない ⇒起訴したくてもできない |
不起訴処分告知書はいつ取得できる?
不起訴処分告知書を取得できるのは不起訴処分が確定した後です。
処分の流れとしては、まず担当の検察官が不起訴とすべき旨の裁定書を作成し、上席検事の決裁に上げます。そこで、不起訴の決裁を受けてはじめて不起訴処分が確定します。
検察庁で取調べを受けた際、検察官から「この事件は不起訴にします」と言われることがあります。そのような発言があっても、不起訴の決裁が下りる前に不起訴処分告知書を取得することはできません。
逮捕・勾留されていなければ、検察官の取調べを受けた日からおおむね1か月以内に起訴・不起訴が確定することが多いです。
逮捕・勾留されている事件であれば、釈放された日に不起訴が確定することが多いです。処分保留で釈放された場合は、釈放された日から1か月以内に不起訴が確定することが多いです。
不起訴処分告知書の取得方法
不起訴処分告知書は、不起訴になれば、待っているだけで自宅に届くわけではありません。取得を希望するのであれば、被疑者の側から請求する必要があります。具体的な取得の仕方は次のとおりです。
1.弁護士がいる場合
弁護士がいる場合は、弁護士に依頼して、不起訴処分告知書を取得してもらうのが一般的です。
刑事事件を数多く扱っている事務所では、依頼者が何も言わなくても、不起訴処分告知書の取得までやってくれることが多いです。ウェルネスでもそのように対応しております。
国選弁護人は被疑者が釈放された時点で業務が終了しますので、不起訴処分告知書の取得までは対応してもらえないことが多いです。
2.弁護士がいない場合
弁護士がいない場合はご自身で請求することになります。請求の仕方については、①郵送による方法と、②検察庁に出向いて検察官や検察事務官から交付を受ける方法の2つがあります。
検察官によって、①でも②でもどちらでも対応してくれるケースと、②の方法しか対応してくれないケースがあります。
自分で請求した場合、どちらかというと②の方法しか対応してくれない検察官が多いようです。ただ、出張中に起こした刑事事件などで検察庁が遠方になる場合は、②の方法で対応してくれることが多いです。
【郵送で請求する場合】
申請書に必要事項を記入し検察官に発送します。切手を貼った返信用封筒も同封してください。検察(事務)官によっては、簡易書留でしか返送してくれない方もいますので、事前に確認してください。
普通郵便で発送してくれる場合は、返信用封筒に貼る切手は84円です。簡易書留でしか返送してくれない場合は、404円分の切手を貼ってください。
【検察庁に出向く場合】
検察事務官とあらかじめ日程調整をした上で、免許証などの身分証明証とシャチハタ以外の印鑑(認め印可)を持参してください。
いずれの方法による場合でもまずは検察官・検察事務官に連絡してください。
検察官の氏名がわからない場合は、検察庁の代表に電話して「被疑者本人ですが不起訴処分告知書を取得するにはどのようにすればよろしいでしょうか?」とお尋ねください。
不起訴処分告知書を取得できないケース
1.(略式)起訴された場合
起訴とは被疑者を刑事裁判にかけることです。起訴されたということは、不起訴になっていないことを意味しますので、不起訴処分告知書を取得することはできません。
罰金刑が定められている軽微な犯罪の場合は、略式裁判という簡単な裁判で罰金になることが多いです。
略式裁判は、書面のみで審理され法廷が開かれないため、「不起訴になった」と誤解されている方もいますが、略式起訴という形で起訴されていますので、不起訴処分告知書を取得することはできません。
(略式)起訴された場合は、裁判所から自宅や勾留中の警察署に起訴状が届きます。
2.不送致の場合
刑事事件の捜査は警察→検察という流れで進みます。検察に事件を引き継いだ後は検察官が必ず起訴するか不起訴にするかを決めることになりますが、「不送致」といって検察に引き継がずに警察限りで事件を終了させることがあります。
不送致の代表的なケースが微罪処分です。
⇒微罪処分とは?流れや対象となる犯罪、デメリットを弁護士が解説
不送致になった場合は、事件が検察に引き継がれないので不起訴になることもありません。そのため、不起訴処分告知書を取得することはできません。
なお、不起訴と異なり不送致の証明書はありませんので、不送致になったことは口頭での確認のみとなります。
3.交通違反の場合
交通違反をして反則金で終わった場合は、刑事事件になっていないので、不起訴処分告知書を取得することはできません。
反則金を払わずに刑事事件に移行した場合、事案が軽微であることを理由として不起訴になることが多いです。その場合は不起訴処分告知書を取得することができます。
赤切符を切られた場合は不起訴ではなく、略式起訴され罰金になるため、不起訴処分告知書を取得することはできません。
不起訴処分告知書の取得費用
1.検察庁の費用
不起訴処分告知書は無料で取得できます。ただ、郵送で申請する場合は、切手を貼った返信用封筒を同封する必要があります。簡易書留を指定された場合は、404円分の切手を貼ってください。
2.弁護士費用
不起訴処分告知書の取得について弁護士費用がかかるかどうかは法律事務所によって異なります。
不起訴処分告知書の取得は、弁護活動というよりは事務手続ですので、弁護士費用が発生するとしても、実費程度のことが多いです。ウェルネス法律事務所では実費も含め無料で告知書を取得しております。
不起訴処分告知書の使用方法
1.公的手続
不起訴処分告知書を公的手続で使用することはありません。
2.その他の手続
①会社への提出
刑事事件が勤務先の会社に知られており、懲戒処分の手続が進行している場合は、会社に不起訴処分告知書を提出することにより、不起訴になった事実を証明することができ、懲戒処分が軽減されることがあります。
会社から「不起訴処分告知書を提出してください」と指示されることもあります。
②外国への提出
ビザや永住権を取得するために不起訴処分告知書が必要になることがあります。
不起訴処分告知書は保管しておくべき?
上で説明した例外を除き、不起訴処分告知書が必要になることはまずありません。そのため、不起訴処分告知書を手元に持っている必要はありません。
不起訴処分告知書を保管しておくことのメリットとデメリットは次の通りです。
【メリット】
常に刑事事件のことを思いだすことにより、自分に対する戒めとすることができる。
【デメリット】
刑事事件になっていることを家族に黙っているケースでは、不起訴処分告知書を家族に見られることにより、事件化していることがばれてしまうリスクがある。
不起訴処分告知書は日常生活に必要なものではなく、紛失等のリスクもあります。そのため、ウェルネスでは希望される方にのみ不起訴処分告知書の原本をお送りしています。
不起訴処分告知書を弁護士が取得します
ビザや永住権を得るためお早めに不起訴処分告知書を取得したい方のために、ウェルネスでは、弁護士が皆様の代わりに不起訴処分告知書を取得します。
不起訴処分告知書の取得費用は3万3000円です(税込)。
*刑事弁護をご依頼されていない方向けのサービスです。
*刑事弁護をご依頼されている方は、不起訴で終了した際、弁護士が無料で不起訴処分告知書を取得し、ご希望によりお渡ししております。
☑ 自分で申請するのが面倒
☑ 検察庁まで来てくれといわれたが時間がない
☑ 検察官が怖かったので話したくない
☑ 弁護士に頼んだが対応してくれなかった
このような方はお気軽にウェルネス(03-5577-3613)へご相談ください。
【関連ページ】