- トップ
- > 略式裁判とは?罰金の金額や払えない場合について弁護士が解説
- > 逮捕・勾留中に罰金となり釈放される流れ
逮捕・勾留中に罰金となり釈放される流れ
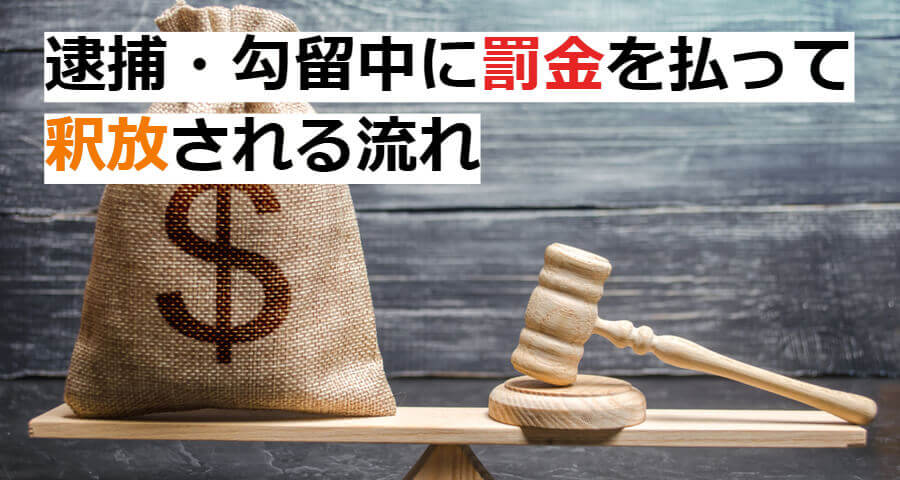
東京23区内で逮捕・勾留された方が罰金となり釈放されるまでの流れを解説しています。他の地域でもおおむね同様の流れになります。
このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。
罰金で釈放されるまでの流れ
1.方針の決定
逮捕・勾留される→検察官が略式起訴する方針を固める。
2.勾留満期の前日頃
①警察署から護送バスで東京地検に行く。
②検察官から略式裁判の説明を受け、同意書に署名・指印する。
⇒略式裁判とは?罰金の金額や払えない場合について弁護士が解説
勾留の満期日は、勾留請求された日(逮捕後に初めて検察庁に行った日)から起算して10日目になります。勾留が延長されれば、最長で勾留請求された日から起算して20日目になります。 |
3.2の翌日
①警察署から護送バスで東京地裁の警視庁同行室に行く。
②検察官が東京簡易裁判所に略式起訴する。
略式起訴されてから略式命令が発付されるまで数時間かかります。その間は同行室で待機してもらいます。 |
③裁判所が略式命令を発付する。
④裁判所書記官が警視庁同行室に来て被告人に略式命令書を交付する。
警察官は略式命令書を送達する権限がないため、裁判所書記官が被告人に直接手渡しします。 |
⑤上記⑥の直後に護送警察官が被告人の手錠を外して釈放する。
略式命令を告知した時点で勾留は失効するため(刑事訴訟法345条)、身柄拘束の根拠がなくなります。そのため、検察官は略式請求する際、「略式命令が発付されたら直ちに釈放のこと」と記載された釈放通知書を護送警察官に交付します。 |
⑥護送警察官と一緒に検察庁に移動する→検察庁2階の罰金の徴収窓口に案内される。
事前に検察官が被告人の家族に電話して、罰金を持参して午後2時頃に検察庁の徴収窓口で待機するよう指示していることが多いです。その場合は家族が罰金を払って手続が終了します。
家族が迎えにきておらず、その場で罰金を払えない場合は、徴収担当の職員から罰金の納付用紙をもらい、後日銀行で納付することになります。この場合、職員から住所や連絡先について確認されます。
罰金を払わなければ最終的には労役場に留置されます。 |
*2と3をまとめて1日で終わらせることもあります。
罰金前科を避けるために
罰金であっても前科はついてしまいます。被害者がいる事件では、被害者と示談をすれば、多くのケースで不起訴となり、前科を回避することができます。
検察官は加害者やその家族に被害者の連絡先を教えてくれないため、示談をするためには弁護士を通じて被害者の連絡先を確認することが必要です。
まずは弁護士にご相談ください。
【関連ページ】




