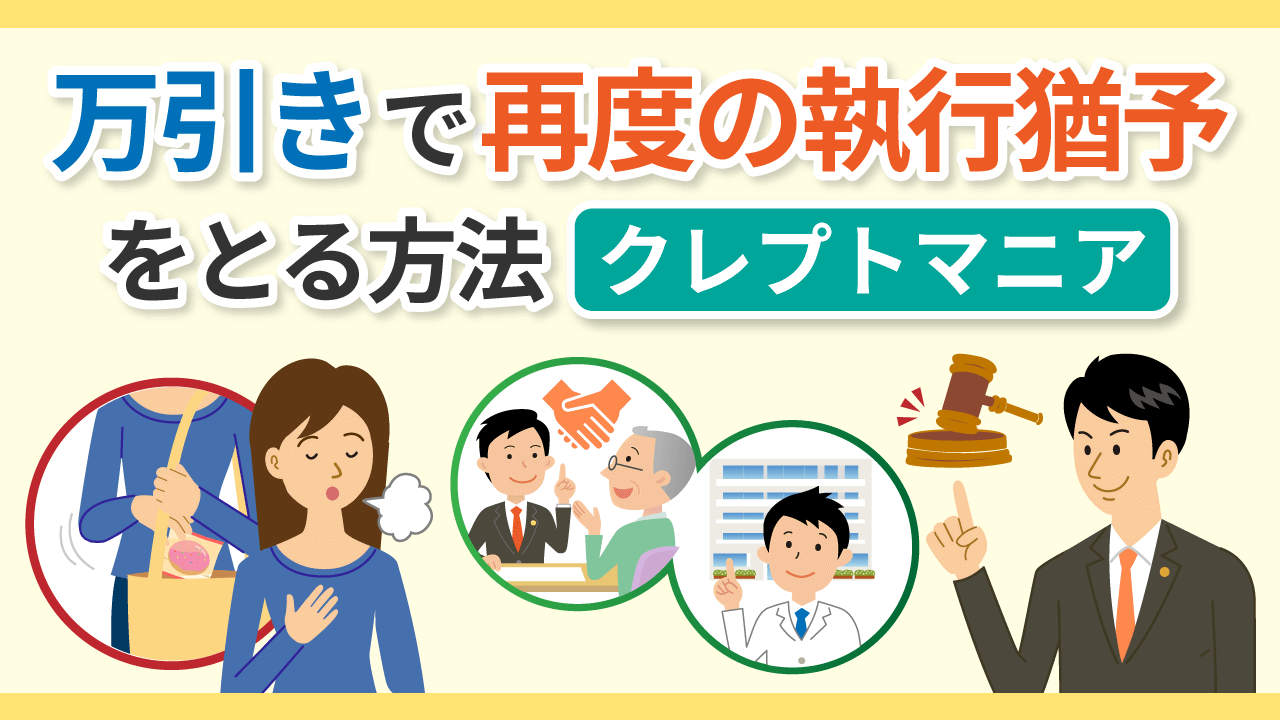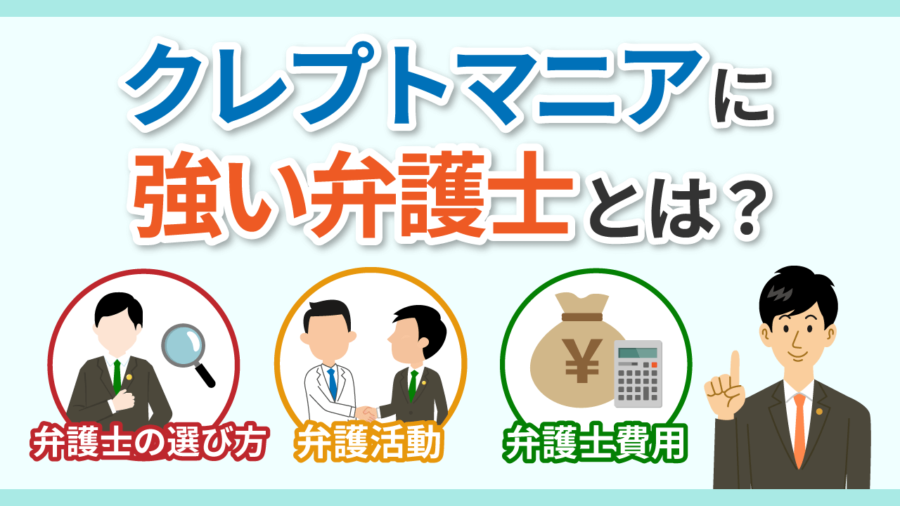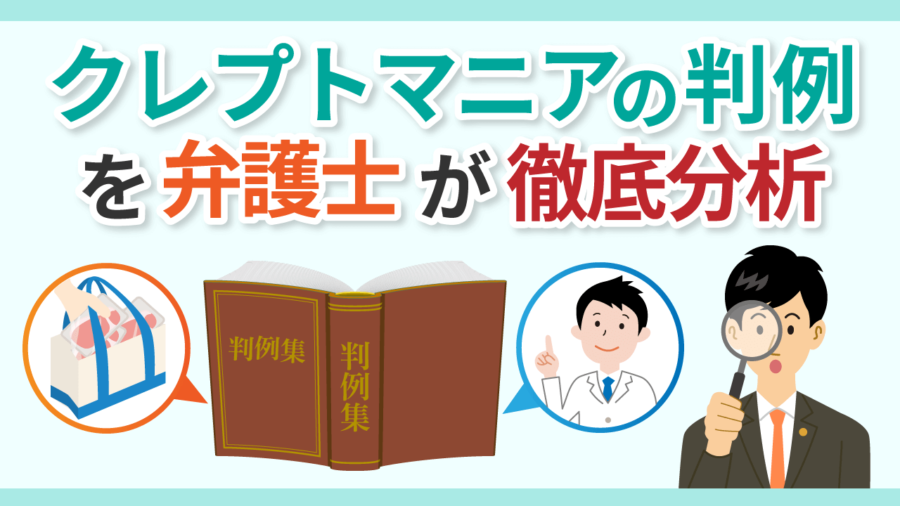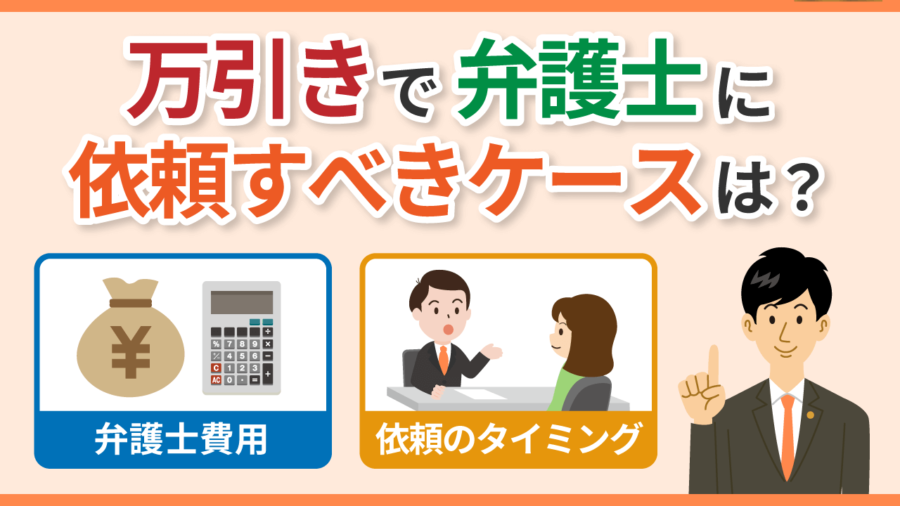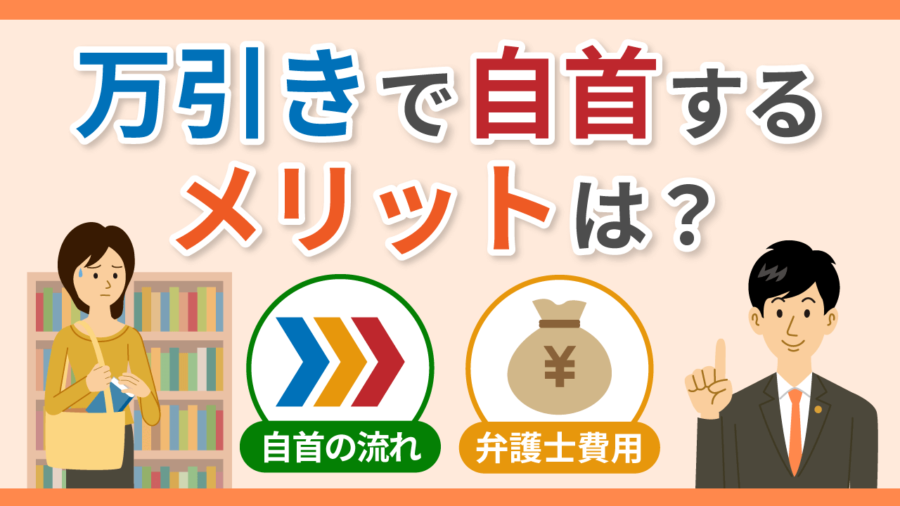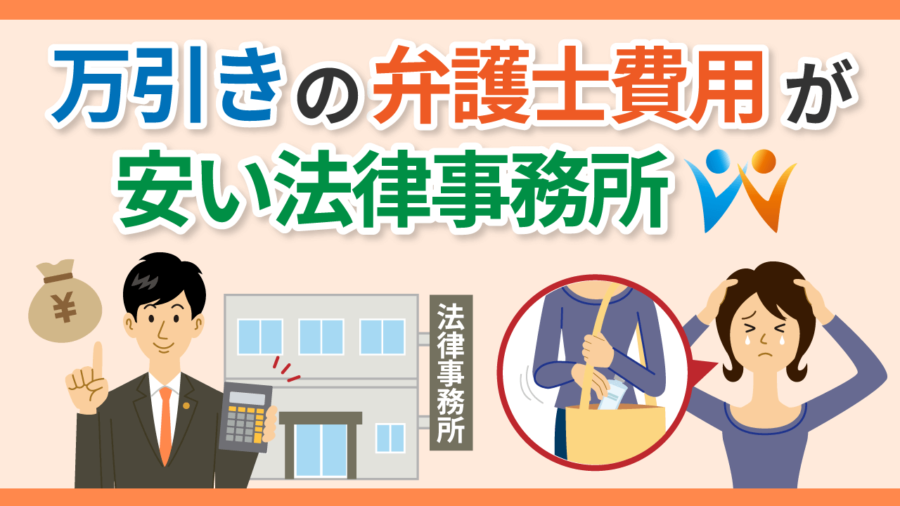- トップ
- > 万引きで弁護士に依頼すべきケースは?弁護士費用や依頼のタイミングも解説
- > 【クレプトマニア】万引きで再度の執行猶予をとる方法を解説
【クレプトマニア】万引きで再度の執行猶予をとる方法を解説
クレプトマニアの方が執行猶予中に万引きをしてしまうことがあります。そのようなケースで再度の執行猶予をとるための方法を弁護士 楠 洋一郎が解説しました。ぜひ参考にしてみてください。
目次
万引きで再度の執行猶予-3つの要件
再度の執行猶予とは執行猶予中に別の事件で起訴され再び執行猶予になることです。執行猶予中に万引きをして起訴された場合、原則として実刑になります。
ただし、次の3つの要件をすべてクリアした場合は、例外的に再度の執行猶予となる余地があります。
①懲役1年以下の判決であること
②特に酌量すべき情状があること
③前回の執行猶予に保護観察が付けられていないこと
保護観察付きの執行猶予中であれば、③の要件をクリアできないため、再度の執行猶予になることはなく実刑になります。保護観察なしの執行猶予中であれば、①と②の条件をクリアすれば、再度の執行猶予(ダブル執行猶予)となる余地があります。
【刑法】
|
万引きで再度の執行猶予-懲役1年以下は可能?
万引きで再度の執行猶予となるためには、判決で言い渡された刑が1年以下の懲役でなければなりません。1年を超えた場合は、他にどれだけ有利な事情があったとしても、実刑になってしまいます。
それではどのような事情があれば懲役1年以下の判決を獲得できるのでしょうか?裁判官が刑罰を決めるプロセスをふまえて解説していきます。
1.刑罰の重さはどのように決まる?
裁判官は刑罰を決めるにあたって、「犯罪行為がどれだけ悪質か」、「犯罪の結果がどれだけ重大か」、「計画性があるか」といった犯罪そのものに関わる事情(犯情)に着目して、「懲役1年から1年6か月」等と大まかな刑罰の範囲を決めます。
次に、犯情以外のさまざまな事情、例えば示談や再犯の可能性、前科の有無といった一般情状を検討した上で、最初に決めた大まかな刑罰の範囲のなかで「この被告人は懲役1年が相当」等と具体的な刑罰を決定します。
このように裁判官は2つのステップで刑罰を決めます。
ステップ① | 犯情から大まかな刑罰の範囲を決める。 |
ステップ② | 一般情状を検討して、ステップ①で決めた範囲の中で具体的な刑罰を決める。 |
2.有利な犯情をもれなく指摘する
執行猶予中の万引きで懲役1年以下の判決を獲得するためには、裁判官が犯情に基づき刑の範囲を決める際に、その中に懲役1年が含まれていることが必須です。
裁判官が「犯情が悪く懲役1年6月~2年がふさわしい」と判断した場合、どんなに有利な一般情状があっても、刑が懲役1年6月を下回ることはありません。
【不利な犯情】
次のような事情があればあるほど犯情が悪くなり、ステップ①で刑の範囲が1年を超えてくる可能性が高まります。
万引きの犯情 | 具体例 |
計画性がある | 店の防犯カメラに店内をグルグル回って様子をうかがっている状況が撮影されている |
営利目的で万引きした | 万引きした物をフリマアプリに出品している |
手口が巧妙である | いったん店のカゴに入れた後、マフラーで隠しながら鞄の中に入れている |
万引きした商品が多い | 食料品を20点万引きした |
被害金額が多い | 被害金額が1万円を超えている |
【有利な犯情】
次のような犯情があればあるほど、刑の範囲に懲役1年が含まれる可能性が高まります。そのため、弁護士としてもこれらの犯情があればもれなく主張する必要があります。
万引きの犯情 | 具体例 |
衝動的である(計画性がない) | 万引きをする前に様子をうかがう等の不審な動きをしていない |
手口が稚拙である | 商品を手にとりそのままポケットに入れて店を出た |
万引きした商品が少ない | パン1個を万引きした |
被害金額が少ない | 被害金額が100円ちょっとである |
3.有利な一般情状を指摘する
特に有利な一般情状は示談と再犯防止の取り組みです。これらの情状は、再度の執行猶予の要件である「特に酌量すべき情状」にもなり得るため、以下この要件との関連で見ていきます。
万引きで再度の執行猶予-「特に酌量すべき情状」とは?
執行猶予中に万引き(窃盗)をして起訴された場合、「特に酌量すべき情状」がなければ、再度の執行猶予を獲得することはできません。「特に酌量すべき情状」になり得る要素として、①示談と②再犯防止の取り組みが挙げられます。
1.示談
万引きのような財産犯のケースでは、被害者の処罰感情が量刑に大きく影響します。そのため、被害弁償を行い示談という形で被害者からの許しを得れば、被告人にとって有利な情状になります。
示談のポイントは示談書に宥恕文言(ゆうじょもんごん)を入れることです。宥恕文言とは「許す」とか「寛大な処分を求める」など処罰感情が和らいでいることを示す文言です。示談をしても宥恕文言がなければ裁判官にあまり評価してもらえません。
2.再犯防止の取り組み
示談が成立すれば「有利な情状」にはなりますが、それだけでは「特に酌量すべき情状」とまでは評価されないことが多いです。
執行猶予中に再び万引きをしてしまったケースでは、加害者の多くはクレプトマニア(窃盗症)に罹患しています。クレプトマニアは精神疾患ですので、本人の意思だけでは「盗りたい」という衝動をコントロールすることができず、再犯のおそれが高いといえます。
そのため、裁判官に「特に酌量すべき情状がある」と認めてもらうためには、再犯防止の取り組みを行い、証拠化することが必要になります。
万引きで再度の執行猶予-再犯防止の取り組みをどうアピールする?
万引きで再度の執行猶予を獲得するためには、裁判官に「特に酌量すべき情状がある」と認められる必要があります。特に酌量すべき情状になり得る要素として再犯防止の取り組みが挙げられます。
1.再犯防止の取り組み状況を証拠化する
万引きの再犯防止の取り組みとしては、クレプトマニア(窃盗症)の治療クリニックに通い、医師の診察や専門家のカウンセリングを受けることが考えられます。
単に通院していればよいというわけではなく、刑事裁判に向けて、取り組みの内容を証拠化しておくことが必要です。具体的には以下のような証拠が考えられます。
証拠の種類 | 具体的な証拠 |
通院したことの証拠 | 医療費の領収証、カルテ |
本人の症状についての証拠 | 医師の診断書 |
通院状況についての証拠 | カルテ、本人作成の報告書 |
再発防止の見込みに関する証拠 | 医師・カウンセラーの意見書 |
このうち最も重要な証拠は医師やカウンセラーの意見書です。
クレプトマニアの治療を担当した医師やカウンセラーが、再犯防止の見込みについて有利な内容を意見書に記載してくれれば、再犯防止の取り組みが「特に酌量すべき情状」として認められる可能性が高まります。
2.意見書を証拠にできないことも
専門家の意見書は再度の執行猶予を獲得するために有用ですが、大きな制約があります。それは、「検察官が意見書の取調べに同意しなければ、裁判の証拠とすることができない」という制約です。
刑事裁判では、相手方の同意がない限り、原則として書面を証拠とすることはできません。供述者の見間違いや記憶違いにより、書面に事実と異なることが書かれている可能性があるからです。
そのため、間違った書面に基づき誤った裁判がなされることがないよう、相手方の同意がない限り、書面を証拠とすることはできないのです。このルールを伝聞法則(でんぶんほうそく)といいます。
相手方が不同意にすれば、その書面を証拠として提出することはできませんが、代わりに供述者の証人尋問を請求することができます。
供述者が証人として出廷すれば、書面と異なり反対尋問をすることで供述の信用性をチェックすることができるため、証人尋問の申請を不同意にすることはできません。
*医療費の領収証やカルテも書面ですが、類型的に誤りがすくない書面として、検察官の同意がなくても証拠にすることができます(伝聞例外)。
3.専門家に証人として出廷してもらう
専門家の意見書を証拠として提出しようとしても、検察官が不同意にすれば提出することはできません。
意見書を不同意にされれば、弁護士は専門家を証人として取り調べるよう請求することができます。専門家自身に法廷に来てもらい、被告人のために有利な事情を話してもらうのです。
もっとも、専門家が必ず証人として出廷してくれるわけではありません。意見書は書いてくれるものの、出廷については消極的な専門家も多いです。出廷してくれるとしても、高額な費用がかかってしまうこともあります。
そのため、クレプトマニアの治療を始める時点で、「裁判になった場合に適正な費用で証人として出廷してくれる」専門家を選ぶべきです。ウェルネスの弁護士がそのような専門家を紹介することも可能です。
ウェルネスではクレプトマニアによる万引きで再度の執行猶予を獲得したケースが複数あります。執行猶予中に万引きをした方やご家族はお気軽に弁護士にご相談ください。
クレプトマニアに強い弁護士が解説!
万引きに強い弁護士が解説!