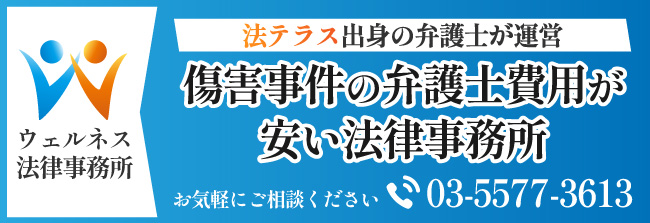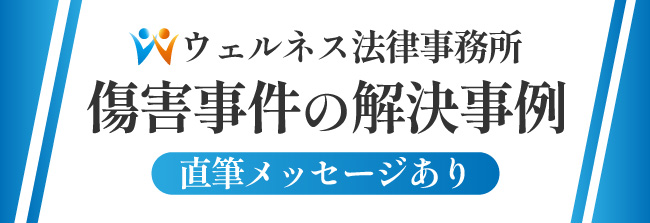- トップ
- > 傷害事件に強い弁護士に相談!傷害の弁護士費用や相談・依頼のメリット
- > 嫌がらせによる傷害事件について弁護士が解説
嫌がらせによる傷害事件について弁護士が解説
嫌がらせが傷害事件になり得るケースとして、無言電話や騒音によって、被害者にPTSD等の精神疾患を生じさせたケースが考えられます。
☑ 交際している男性の元彼女に繰り返し無言電話をかけPTSDに罹患させた。
☑ 隣家に向けて大音量でラジオを流して隣人をノイローゼにさせた。
このような嫌がらせの事例における傷害罪の成否や刑事手続の流れ、弁護活動について弁護士 楠 洋一郎が解説しました。ぜひ参考にしてみてください。
嫌がらせによる精神疾患が「傷害」といえるか?
殴ったり蹴ったりしてケガをさせた場合は、傷害罪が成立することは明らかです。
それでは、嫌がらせによって被害者がPTSDやノイローゼ、うつ病等に罹った場合、これらの精神疾患も「傷害」といえるのでしょうか?
傷害罪における「傷害」の典型的な例は、打撲や擦り傷、骨折など目やレントゲンで認識できるケガです。これに対して、PTSDやノイローゼ、うつ病などの精神疾患は視覚的に認識できるケガではありません。
もっとも、傷害罪の傷害は、外傷だけではなく生理的機能の障害全般を意味します。PTSDやノイローゼ、うつ病などの精神疾患であっても、生理的機能が障害されたといえるので、傷害にあたります。
嫌がらせは傷害の実行行為といえるか?
1.無形的方法であっても傷害の実行行為になり得る
傷害罪の最もよくあるケースは、加害者が被害者を殴ったり蹴ったりして打撲や骨折などのケガをさせるケースです。
もっとも、傷害罪の条文上は、傷害の手段が暴行に限定されているわけではありません。
【刑法204条】 人の身体を傷害した者は、15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。 |
*2025年6月1日以降に発生した事件については、懲役刑ではなく拘禁刑が適用されます。
そのため、暴行のような有形力を行使する方法だけでなく、嫌がらせのような物理的な圧力を加えない無形的方法による傷害も認められます。
2.傷害の実行行為性は個別に判断する
嫌がらせのような無形的方法も傷害の手段として認められていますが、嫌がらせであれば何でも傷害罪の実行行為といえるわけではありません。
上で説明したように、傷害罪の「傷害」とは人の生理的機能に障害を与えることです。そのため、生理的機能に障害を与える現実的な危険性があって初めて傷害罪の実行行為といえます。
嫌がらせにこのような現実的な危険性があるかどうかは、嫌がらせの期間や頻度、嫌がらせの内容、被害者の状況などから個別に判断されます。
嫌がらせによる傷害事件の判例
判例では、嫌がらせに関して、以下のような事情が認定されています。
判例①(名古屋地裁平成6年1月18日)
嫌がらせの相手 | 元上司 |
嫌がらせの期間 | 約7カ月 |
嫌がらせの頻度 | ほぼ連日 |
嫌がらせの内容 | 被害者の自宅付近を徘徊し「ばかやろう」等と怒鳴る、ダンプカーで被害者宅の玄関先に行き急停車したり空ぶかしをする、自転車のベルを鳴らす等 |
被害者の状況 | 入院加療約3か月を要する不安及び抑うつ状態 |
その他の事情 | 同じ被害者に対する犯罪で過去に3回服役している |
判例②(富山地裁平成13年4月19日)
嫌がらせの相手 | 交際している男性の元恋人 |
嫌がらせの期間 | 約3年半 |
嫌がらせの頻度 | 数日おきないしは連日 |
嫌がらせの内容 | 無言電話、「死ね」等と中傷する電話を合計1万回以上かけた |
被害者の状況 | PTSD |
その他の事情 | 器物損壊や被害者の家族が経営する店に対する威力業務妨害でも起訴されている |
判例③(最高裁平成17年3月29日)
嫌がらせの相手 | 隣人 |
嫌がらせの期間 | 約1年半 |
嫌がらせの頻度 | 連日朝7時頃から翌日午前2時頃まで |
嫌がらせの内容 | ラジオを隣家に向けて大音量で鳴らす、複数の目覚まし時計を断続的に鳴らす |
被害者の状況 | 全治不詳の慢性頭痛症 |
その他の事情 | 家族や警察官が制止しても一切聞かない |
嫌がらせによる傷害事件と故意
暴行による傷害事件の場合は、「ケガをさせる」ことについての故意がなくても、「暴行すること」についての故意があれば、傷害罪は成立します。
これに対して、嫌がらせのような無形的方法による傷害の場合は、「ケガをさせること」自体についての故意が必要となります。
故意の内容としては、「嫌がらせにより特定の病気を発症することの確定的な認識」までは必要ありません。
「嫌がらせにより正常な活動ができなくなり日常生活に支障がでるかもしれない」という程度の認識があれば、ケガをさせることについての、未必の故意があったと認められます。
そのような認識があったか否かは、主として嫌がらせの客観的な状況から判断されます。上で紹介した判例のケースでは、嫌がらせの期間・頻度・内容等に照らして、いずれも傷害の故意が認められました。
嫌がらせによる傷害事件と逮捕
嫌がらせの被害者が警察に被害届を出そうとしても、個人間のトラブルとして、なかなか受理してもらえません。
そのため、嫌がらせが刑事事件になるのは、非常に悪質で、被害者が精神疾患などに罹患していることが前提となります。
そのようなケースで、被害届が提出されて刑事事件になると、逮捕される可能性が高いです。
嫌がらせによる傷害事件では、加害者は被害者に対して強い敵意や恨みを持っており、逮捕しなければ、加害者がより激しい嫌がらせをするおそれがあるからです。
嫌がらせによる傷害事件で逮捕された後の流れ
1.勾留される可能性が高い
逮捕は最長3日ですので、勾留されない限り3日以内に釈放されます。もっとも、嫌がらせによる傷害事件の加害者は、より激しい嫌がらせをするおそれがあるため、勾留される可能性が高いです。
勾留されると原則10日にわたって拘束されます。勾留が延長されればさらに最長10日わたって拘束されます。
この間に被害者との間で示談が成立すれば、釈放され不起訴になる余地があります。示談が成立しなければ、起訴される可能性が高いです。
2.公判請求される可能性が高い
暴行による傷害事件では、被害者が軽傷の場合は、略式起訴されて罰金刑で終わることが多いです。
これに対して、嫌がらせによる傷害事件では、事件化する段階で悪質なケースに絞られていることもあり、公判請求されることが多いです。公判請求されると公開の裁判で審理され、検察官から拘禁刑を請求されることになります。
また、保釈が許可されない限り、裁判が終了するまで勾留が続きます。保釈請求が許可されるためには、家族一丸となって本人を監督し、再発防止のための説得的なプランを実行する必要があります。
嫌がらせによる傷害事件は執行猶予?実刑?
嫌がらせによる傷害事件は、事件化の段階で悪質なものに絞られていますが、その中でも嫌がらせの期間・頻度・態様においてとりわけ悪質なケースでは、初犯であっても実刑になることがあります。
上で紹介した判例②のケースでは、加害者に前科はありませんでしたが、懲役1年8月の実刑判決が確定しました。
嫌がらせによる傷害事件の弁護活動
1.被害者と示談をする
嫌がらせによる傷害のケースでは、被害者に多大な被害を与えているからこそ、示談という形で被害者から許しを得たということが、処分を決める上で大きな意味を持ちます。
示談が成立することにより不起訴や執行猶予を獲得できる可能性が高くなります。嫌がらせによる傷害事件の被害者は、加害者と一切関わりたくないと思っているので、示談交渉は弁護士が行うことになります。
示談金の額は、治療費・通院交通費・休業損害のほか、相当な金額の慰謝料が必要となるでしょう。
2.クリニックへ通院する
嫌がらせによる傷害のケースでは、加害者が被害妄想など何らかの精神的な問題を抱えていることが少なくありません。
治療しないで放置すると、仮に執行猶予になったとしても、猶予期間中に再犯してしまい実刑になることもあります。そうなれば執行猶予も取り消されてしまいます。
上で紹介した判例①のケースでは、被告人は過去にも3回、同じ被害者に対する嫌がらせで服役しており、判決書で「結局は被告人も被害者に対する嫌がらせに終始した期間自らの人生を浪費したのみで何ら得るところがなく、取り返しのつかない損失を被った」と書かれています。
保釈後にクリニックに通院し、医師や心理士のサポートを受けながら、心の問題に向き合うことが必要です。弁護士が検察官や裁判官に医師の診断書や通院証明書を提出して、不起訴や執行猶予を求めます。
3.家族に監督してもらう
嫌がらせによる傷害のケースでは、加害者も生活の多くの部分を嫌がらせに費やしているため、日常生活のなかで家族に監督してもらうことが必要です。
隣人に対する嫌がらせのケースでは、家族に協力してもらい転居も含めて検討した方がよいでしょう。
弁護士が検察官に家族の監督プランを記載した書面を提出したり、家族に情状証人として出廷してもらい、どのように監督していくかを裁判官に話してもらいます。
傷害に強い弁護士が解説!