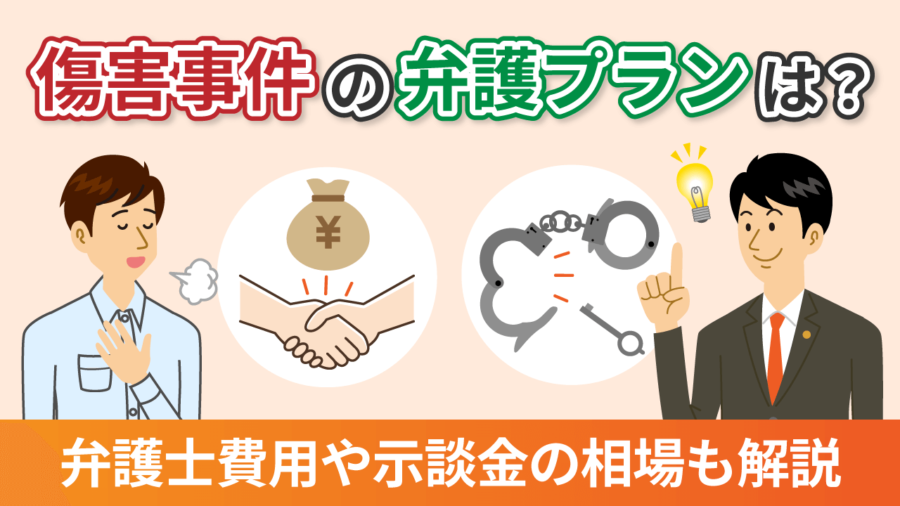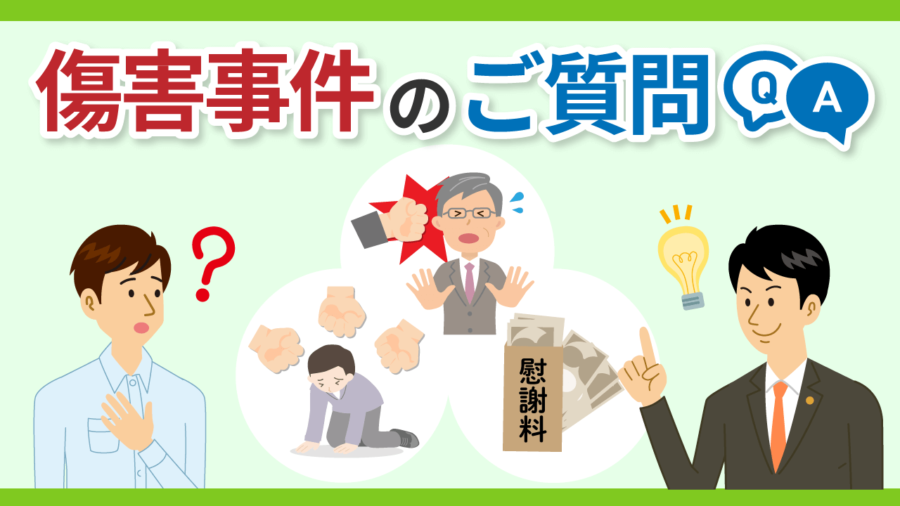- トップ
- > 傷害の無料相談は弁護士へ-無料相談の窓口やポイントを解説
- > 正当防衛はどこまで認められる?成立要件や過剰防衛について
正当防衛はどこまで認められる?成立要件や過剰防衛について
このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。
正当防衛が認められるとどうなる?
1.正当防衛が成立すると犯罪にならない
暴行・傷害事件で正当防衛が問題になることがあります。たとえ暴力をふるったり、ケガをさせても、正当防衛が成立すると暴行罪や傷害罪にはなりません。
なぜ暴行罪にも傷害罪にもならないのでしょうか?それは、正当防衛が違法性阻却事由(いほうせいそきゃくじゆう)にあたるからです。
2.違法性阻却事由とは
犯罪が成立するためには、加害者の行為がそれぞれの犯罪を構成する要件(「構成要件」といいます)に該当する必要があります。
もっとも、たとえ全ての構成要件に該当していても、その行為に違法性が認められなければ、犯罪は成立しません。違法性が否定される事情のことを「違法性阻却事由」(いほうせいそきゃくじゆう)といいます。
例えば、医師が手術をするために患者の身体にメスを入れることは、傷害罪の構成要件に該当しますが、「正当業務」として違法性が阻却されるため、傷害罪は成立しません。このように違法性が否定されると犯罪にはならないのです。
3.正当防衛も違法性阻却事由
正当防衛も違法性阻却事由のひとつです。そのため、構成要件に該当しても正当防衛が成立すれば、違法性が否定され犯罪は成立しません。
暴行罪の構成要件は、「人に対して有形力を行使すること」です。傷害罪の構成要件は、「人の生理的機能に障害を与えること」です。
これらの構成要件を満たしていても、正当防衛が成立すれば、違法性がなく暴行罪や傷害罪にはならないのです。
正当防衛の成立要件
正当防衛が成立するためには次の3つの要件を全て満たす必要があります。
1.急迫不正の侵害があること
正当防衛が認められるためには、防衛行為に出た者が現に侵害を受けているか、侵害が差し迫っていることが必要です。例えば、いきなり酔っ払いに殴りかかられた場合は急迫不正の侵害があるといえるでしょう。
過去の侵害は急迫性が否定されます。侵害が現に差し迫っていれば、防衛行為に出た者が侵害を予期していたとしても、それだけで急迫性は否定されません。
2.防衛の意思があること
正当防衛が認められるためには、自己または他人の権利を防衛する意思が必要です。正当防衛は冷静に考えて行うものではなく、反射的・本能的に行われるため、防衛の明確な意図までは不要です。
また、怒りで逆上して反撃行為に出たとしても、それだけで防衛の意思が否定されるわけではありません。怒りと防衛の意思は併存し得ると考えられているからです。
3.やむを得ずにした行為であること
正当防衛が成立するためには、防衛行為をやむを得ずにしたことが必要になります。もっと危険性が低い防衛行為をとることができたのに、あえて危険性の高い行為に及んだ場合は、やむを得ずにした行為とは認められず、正当防衛は成立しません。
「もっと危険性が低い行為をとることができたか」は、当事者の年齢・性別・身長・体格・緊急性・危険性の程度、凶器の種類、周囲の状況などを総合的に判断して決められます。
正当防衛はどこまで認められる?過剰防衛との境界は?
1.過剰防衛とは
過剰防衛とは行き過ぎた防衛行為のことです。正当防衛の3つの要件のうち、「やむを得ずにした行為であること」という要件を欠く場合は過剰防衛となります。
「急迫不正の侵害」や「防衛の意思」がない場合は、正当防衛にも過剰防衛にもあたりません。過剰防衛には質的な過剰防衛と量的な過剰防衛があります。以下それぞれについて見ていきましょう。
2.質的な過剰防衛
質的な過剰防衛とは、拳で殴りかかられてナイフで反撃するように防衛手段が相当性を欠く過剰防衛です。
「武器対等の原則」と言って、素手に対して素手、刃物に対して刃物であれば正当防衛は認められやすいですが、素手に対して刃物であれば質的な過剰防衛と見なされやすくなります。
3.量的な過剰防衛
武器対等であっても、相手が攻撃をやめた後も反撃を続けた場合は、量的な過剰防衛になります。例えば、相手が手を出すのを止めた後も殴り続けてボコボコにした場合は、量的な過剰防衛になります。
4.過剰防衛が成立するとどうなる?
過剰防衛が成立すると情状により刑が減軽されるか免除されます。
【刑法】
|
正当防衛を主張したらどうなる?
1.起訴前-起訴される?不起訴になる?
暴行・傷害事件で弁護士が正当防衛を主張し、検察官がその主張をくつがえすのが難しいと判断したときは、不起訴処分になります。
不起訴処分にはいろいろな種類がありますが、正当防衛に関連して不起訴になる場合として、「罪とならず」と「嫌疑不十分」の2つが考えられます。正当防衛になることが明白な場合は「罪とならず」により不起訴処分になります。
防衛行為に行き過ぎがあり過剰防衛の疑いがあるが、それを証明できる十分な証拠がない場合は「嫌疑不十分」により不起訴処分になります。
過剰防衛であることが明らかな場合、起訴することは可能ですが、被害者側の落ち度や被疑者の反省状況などをふまえて、あえて起訴しないこともあります。この場合は起訴猶予で不起訴処分にします。
上記のいずれにも該当しない場合は、起訴される可能性が高いです。
2.起訴後-有罪?それとも無罪?
正当防衛を主張しているケースで起訴される場合、正当防衛の成否について弁護側にも主張・立証の機会を与える必要があるため、正式起訴され公開法廷で審理されます。
刑事裁判では、検察官が犯罪の立証責任を負っています。そのため、「正当防衛であること」を弁護士が立証する必要はなく、検察官が「正当防衛ではないこと」を立証しなければなりません。
とはいえ、裁判で被告人や弁護士が正当防衛について何も主張しなければ、「正当防衛ではないこと」を前提として審理され判決が下されます。
そのため、正当防衛について審理してもらうためには、被告人や弁護士から、正当防衛であると主張することが必要です。被告人や弁護士が正当防衛であると主張すれば、今度は、検察官が「正当防衛ではないこと」を立証することになります。
検察官は、正当防衛ではなかったことを立証するため、防犯カメラ映像を証拠として提出したり、法廷で被害者や目撃者の証人尋問を行います。
これに対して、弁護士は被害者や目撃者に反対尋問を行い、証言の信用性を争ったり、被告人質問で、正当防衛となるような事情があったことを被告人に説明してもらいます。
裁判で正当防衛の主張が認められた場合は、犯罪が成立しないため、無罪判決が言い渡されます。
正当防衛で不起訴を獲得するには?
急迫不正の侵害であること、防衛の意思があること、やむを得ない行為であることの3つの要件を満たせば、正当防衛であると認められます。
もっとも、実務ではこれら全ての要件を満たしているケースは少ないです。不起訴を獲得するためには、正当防衛であることを主張しつつ、たとえ過剰防衛と認定されたとしても、起訴猶予で不起訴となるよう活動すべきです。
そのためには相手方と示談をまとめることが有用です。本人が相手と直接示談交渉をすると更なるトラブルに発展して収拾がつかなくなることがあるため、示談交渉は弁護士にお任せください。
過剰防衛が問題になるケースでは、相手にも落ち度があるといえるため、低額で示談がまとまることも少なくありません。まずは正当防衛の経験豊富な弁護士へご相談ください。
【暴行のページ】
【傷害のページ】