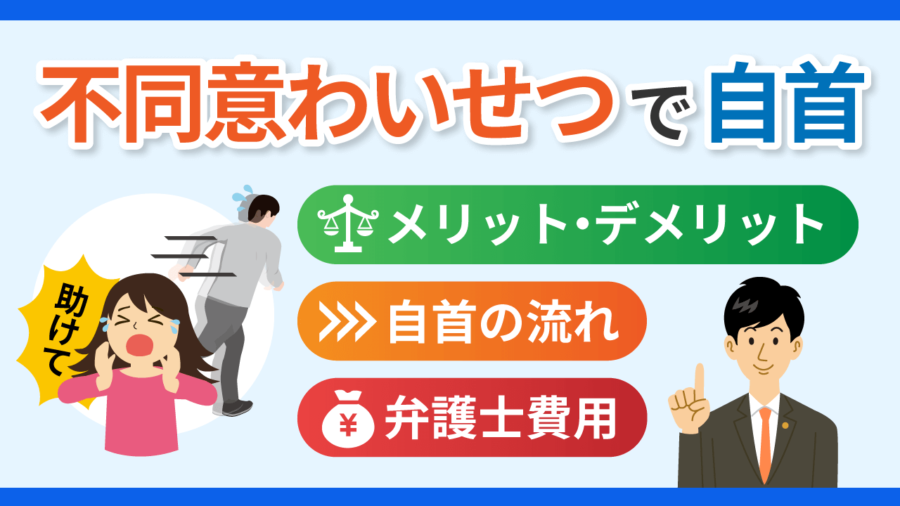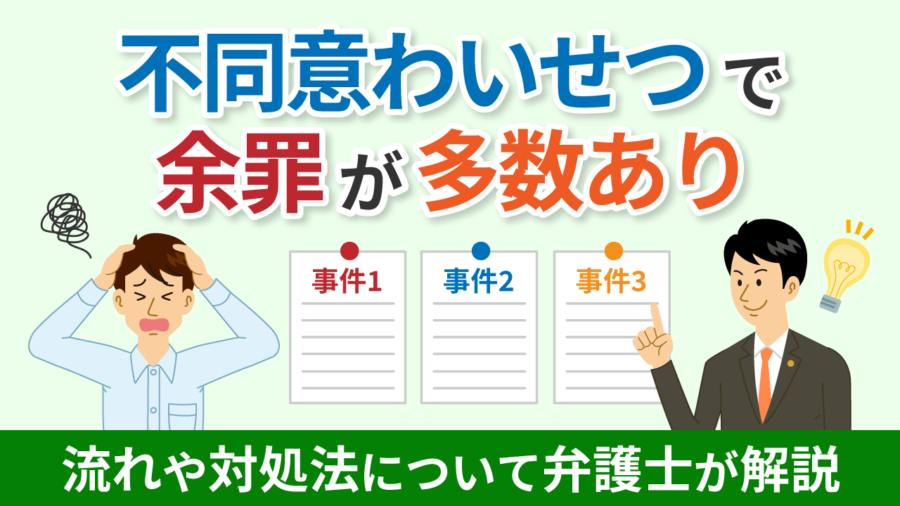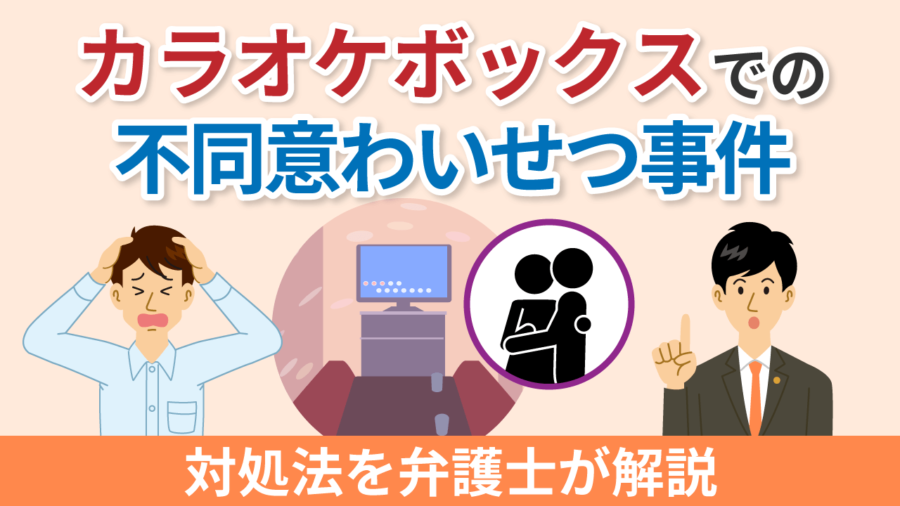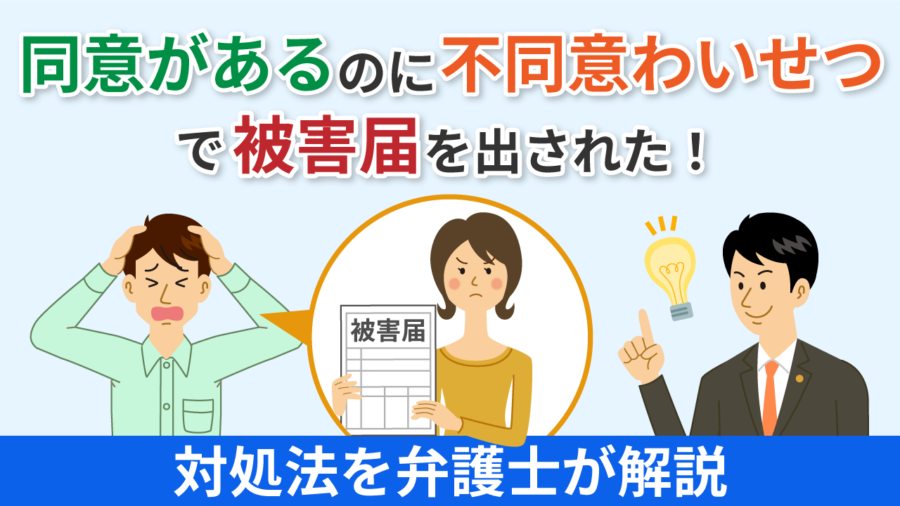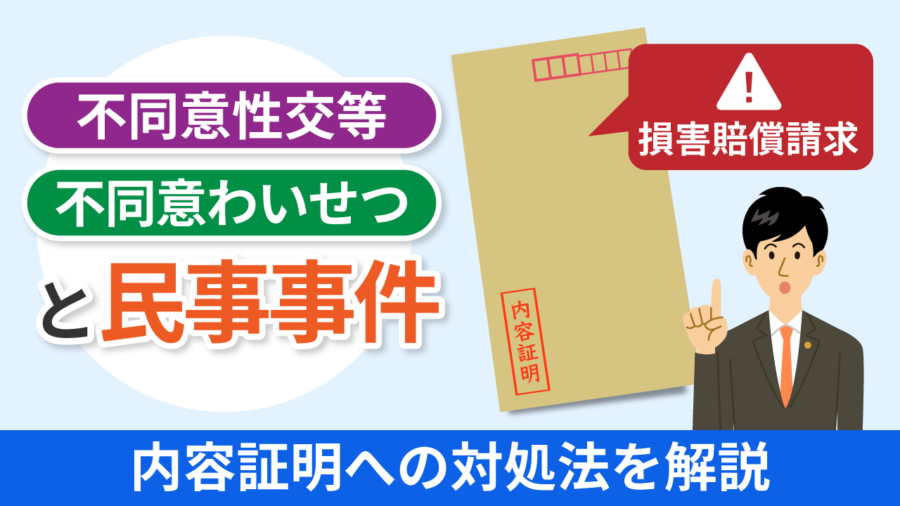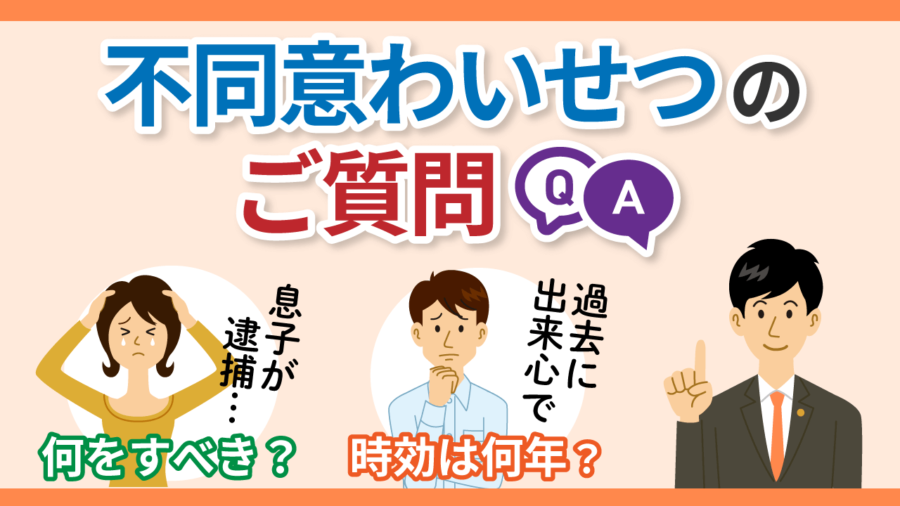- トップ
- > 不同意わいせつに強い弁護士とは?選び方や弁護士費用を解説
- > 子どもに対する不同意わいせつ-逮捕・報道について弁護士が解説
子どもに対する不同意わいせつ-逮捕・報道について弁護士が解説

このページでは16歳未満の子どもに対する不同意わいせつについて、弁護士 楠 洋一郎が解説しています。
目次
このページでは16歳未満の児童のことを「子ども」と表記しています。
子どもに対する不同意わいせつの成立要件
1.相手が13歳未満の場合
相手にわいせつ行為をするだけで不同意わいせつ罪が成立します。たとえ相手の同意があっても不同意わいせつ罪になります。
13歳未満の子どもは、性的な行為の意味を理解する能力がなく、有効な同意をすることができないからです。
2.相手が13歳以上16歳未満の場合
わいせつ行為をした者が5歳以上年長の場合に限り、不同意わいせつ罪が成立します。
13以上16歳未満の子どもは、性的な行為の意味は理解できるものの、相手との関係が対等でなければ、相手との性的行為が自分に与える影響を理解することができないと考えられます。
そのため、発達心理学等の知見にもとづき、5歳以上年長であれば対等の関係にはなり得ないといえることから、13歳以上16歳未満の子どもについては、5歳以上の年長者に限り不同意わいせつ罪が成立するとされました。
子どもに対する不同意わいせつ-16歳未満と知らなかった場合
1.16歳未満であることの認識が必要
16歳未満の子どもに対してわいせつ行為をしても、16歳未満であると認識していなければ、不同意わいせつ罪は成立しません。
例えば、相手から「16歳」と言われて合意の上でわいせつ行為をしたところ、実は15歳だった場合は、16歳未満であることの認識はないので、不同意わいせつ罪は成立しません。
2.未必的な認識で足りる
子どもに対する不同意わいせつ罪が成立するためには、16歳未満であると認識している必要があります。
もっとも、「16歳未満に違いない」といった確定的な認識である必要はなく、「もしかしたら16歳未満かもしれない」という未必的な認識で足りるとされています。
例えば、相手から「高1です」と言われた場合、一般的には高校1年生の中には15歳の人もいるため、特別の事情がない限り、16歳未満であることの未必的な認識があると言えます。
3.取調べでの対応に注意
16歳未満との認識がなかった場合でも、取調べで、「そんなはずないだろ!」と捜査員から厳しく追及されることが多いです。
プレッシャーに負けて「15歳かもしれないと思っていました」といった内容の調書をとられてしまうと、その後に年齢の認識について争うことが難しくなります。
弁護士が取調べに同行する等して本人をサポートし自白調書をとられないようにします。
4.他の犯罪になる可能性も
16歳未満であることの未必的な認識もなければ、相手の同意がある限り、不同意わいせつ罪は成立しません。
もっとも、18歳未満であることの未必的な認識があれば、淫行条例違反(お金を渡していない場合)や児童買春(お金をわたしている場合)が成立します。
子どもに対する不同意わいせつの刑罰は?
子どもに対する不同意わいせつ罪の刑罰は、通常の不同意わいせつ罪と同じで、6か月以上10年以下の拘禁刑(2025年までは懲役刑)です。
もっとも、子どもに対して不同意わいせつをした場、実際に下される処断刑は、一般の不同意わいせつに比べ重くなる傾向があります。
子どもに対する不同意わいせつは、子どもの健全な成長に深刻な影響を与えることが多く、裁判官に悪質と評価されやすいためです。
子どもに対する不同意わいせつと撮影行為
1.わいせつ行為中に撮影するケースが多い
子どもに対する不同意わいせつの特徴として、<わいせつ行為中に子どもの様子を携帯電話などで撮影していることが多い>という点が挙げられます。
小児性愛の傾向がある人は、自分よりも弱い存在を支配したいという欲求を持っていることが多く、撮影した画像を保存するという行為を通じて、歪んだ支配欲を充足しようとする傾向があります。
また、子どもはわいせつな行為をされているという意識がなく、カメラを向けられても避ける動作をしないため、撮影しやすいという面もあります。
2.わいせつ行為中に撮影した場合の犯罪
わいせつ行為中に子どもの性的な部位などを撮影した場合、不同意わいせつ罪とは別に撮影罪が成立します。
撮影罪の刑罰は、3年以下の拘禁刑(2025年までは懲役刑)または300万円以下の罰金です。
3.わいせつ行為中に撮影した場合の刑罰
不同意わいせつ罪と撮影罪の両方で起訴された場合は、併合罪(刑法45条)になります。
【刑法45条】
|
その結果、最高刑は、懲役10年(不同意わいせつの最高刑)+懲役3年(撮影罪の最高刑)=懲役13年となり、この範囲で処断刑が決まります。
【刑法47条】
|
子どもに対する不同意わいせつで逮捕される?
不同意わいせつの前身である強制わいせつについてみると、2021年の強制わいせつ罪の逮捕率は54%ですが、子どもに対する強制わいせつに限ると、逮捕率がさらに高くなると思われます。
逮捕率が高くなる理由は次の2つです。
①子どもは、被害を受けたという意識がなく警戒心が薄いため、証拠隠滅が容易である(「この間のことは2人だけの秘密なので他の誰にも言っちゃだめだよ」といった口裏合わせをするおそれがある)。
②子どもに対して不同意わいせつをした人は、小児性愛の傾向をもっていることが多く、逮捕しないと第2、第3の事件が発生するおそれがある。
子どもに対する不同意わいせつで報道される?
子どもに対する不同意わいせつで逮捕した場合、報道されることが多いです。
子どもは警戒心が薄く、犯罪行為に対して自己防衛することが難しいため、同種事犯の再発を防止するためには、報道することにより、保護者を含めた地域社会に広く注意喚起する必要があるためです。
【関連ページ】
子どもに対する不同意わいせつ-自首して逮捕・報道を回避する
子どもに対する不同意わいせつのケースでは、犯人として特定されれば、逮捕・報道される可能性が高いです。もっとも、自首すれば逮捕・報道を避けられる余地が十分にあります。
逮捕の要件は、逃亡のおそれと証拠隠滅のおそれですが、自首という形で自発的に警察に出頭し正直に話すことにより、これらのおそれが低いと判断されやすくなるためです。
逮捕されなければ、有名人でない限り、報道されることはありません。ウェルネスの弁護士は、子どもに対する複数のわいせつ事件で、自首に同行することにより、逮捕や報道を回避した実績があります。
犯人として特定されれば、その後に出頭しても自首にはなりません。自首を検討されている方はお早めに弁護士にご相談ください。
【自首のページ】
不同意わいせつで自首するメリット・デメリットや自首の流れを弁護士が解説
子どもに対する不同意わいせつと示談
子どもに対する不同意わいせつのケースで最も重要な弁護活動は、被害者側と示談をまとめることです。この点は16歳以上の方に対する不同意わいせつと同じです。
不同意わいせつ罪は起訴にあたって告訴が必要となる親告罪ではないため、示談をしたからといって不起訴が保証されるわけではありません。
子どもに対する不同意わいせつ罪は悪質と評価されやすく、示談が成立しても起訴されることがあります。
不起訴の可能性を高めるために、示談書に「許す」とか「処罰を望まない」といった宥恕文言(ゆううじょもんごん)を入れてもらえるよう、弁護士が被害者の保護者と交渉します。
起訴後であっても示談が成立すれば執行猶予の可能性が高まります。示談が成立していないと損害賠償命令を申し立てられる可能性があるので、起訴後であっても示談はしておいた方がよいでしょう。
【関連ページ】
子どもに対する不同意わいせつと再犯防止
子どもに対して不同意わいせつをした方の中には、根深い小児性愛の傾向を持っている方が少なくありません。再発防止を徹底するためには、専門家のサポートを受けた方がよいでしょう。
逮捕・勾留されている方であっても、東京などの大都市圏であれば、専門家の出張カウンセリングを受けられる場合もあります。
ウェルネスの弁護士がそのような専門家を紹介することも可能です。弁護士が治療経過を証拠化し裁判所に提出したり、専門家に証人として出廷してもらい、カウンセリングの状況や再犯の可能性について証言してもらうことも可能です。
不同意わいせつに強い弁護士が解説!